相続対策
コンシェルジュサービス

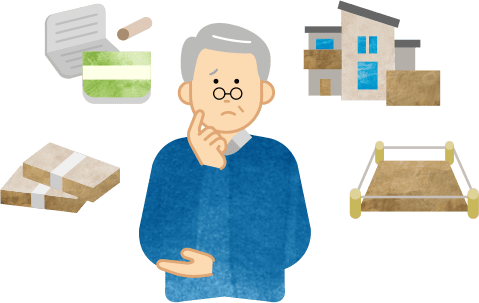
遺言の書き方や、
相続のやり方が分からない
将来、子どもの間で
遺産争いが起こることを避けたい
血縁のない人にも
自分の財産を渡したい
可能な限り相続税を安くしたい
慈善団体に寄付をしたい
相続税がどれくらいかかるか分からない
不動産の手続きが分からない
生前の相続に関するお悩みを
抱えてませんか?
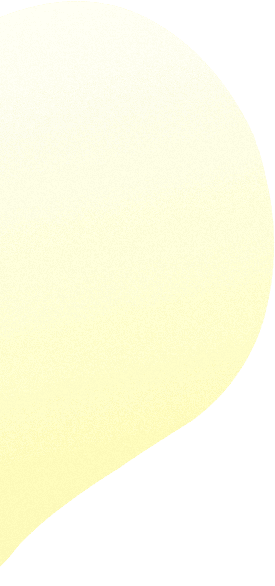

「生前対策」という方法で
相続対策コンシュルジュが
あなたの不安を解消します!
相続税対策・生前対策を考える
3つのチェックポイント
相続税は、将来どれくらいかかりますか?
まずは、どれだけ相続税がかかるかを把握し、その上で必要な対策を検討します。
持っている財産は不動産と預金どちらが多いですか?
不動産が多い、預金が多いなど財産の種類によって適切な対策方法が違います。
争続にしないための事前対策はできていますか?
相続が発生した後に、もめないような財産の分け方をアドバイスいたします。

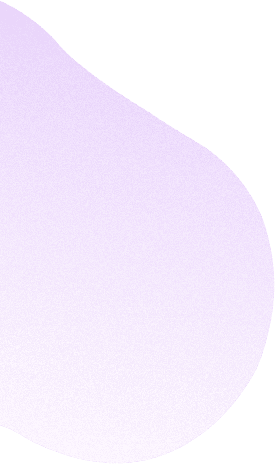

相続対策コンシェルジュサービス
200,000円(税別)
- 相続税簡易シミュレーション
- 相続対策コンサルティング
- 遺言、贈与契約案のご提案
- 遺言書の作成
- 公証役場への立会い
- 贈与契約書の作成
- 贈与登記(1物件)
- 相続対策保険のご提案
相続対策の設計(相続発生後に向けた準備)
ご家族関係や財産状況に応じて、必要な対策や手順は異なります。将来の遺産分けをイメージすることで、今すべき対策や施策がはっきりします。
推定相続人の調査・確定(戸籍の収集と相続関係説明図の作成)
相続対策のためは、本人が亡くなった際の相続人は誰か、相続分はどれ位あるかを確認しておく必要があります。
推定相続人を確認するために必要な戸籍等の収集を行い、相続関係説明図を作成します。
相続税シミュレーション(相続税診断)
相続税が将来かかる可能性があるか、かかる場合はどれくらいの金額になるのかを計算します。
シミュレーション後には、計算書をお渡しいたします。※相続税診断、相続税対策のご提案は、提携税理士が、担当します。
遺言作成(遺言内容の検討、草案作成)
遺言は、決められた書式や内容を守らなければ無効となってしまいます。また、遺言がある故に争いになってしまうことは避けるべきです。専門家が想い実現のためのサポートを行います。
遺言を作成する
5つのメリット
- 遺産分割協議が不要
- 相続人たちの遺産争いを防げる
- 相続後の手続きがスムーズ
- 相続人以外の人や団体に財産を渡せる
- 自分の想いを死後も実現できる
公証役場対応(遺言が有効に作成されるための手続き)
遺言作成後、公証役場からの修正指示の対応や、公証役場での証人立会いなど遺言作成に必要な各所との手続きを代行します。
贈与契約書作成と金銭受け渡しのアドバイス(口座間の金銭受け渡しについて)
単に他の口座に送金するだけでは、「みなし贈与」と呼ばれるように、贈与とはみなされずに税務局から却下されることがあります。贈与契約書の作成と正しい手続き方法をアドバイスします。
税理士の紹介(相続税が将来かかる見込みのあるお客様)
単に他の口座に送金するだけでは、「みなし贈与」と呼ばれるように、贈与とはみなされずに税務局から却下されることがあります。贈与契約書の作成と正しい手続き方法をアドバイスします。
保険による節税対策
生命保険を活用することで、手軽に節税及び相続対策ができます。相続対策をきっかけに、今までかけてきた保険の見直しも可能です。
遺産整理のサポートもお任せください
家業、家屋、土地・田畑や先祖のお墓の管理や相続のことなど、ご家庭事情により財産の種類、遺産分割の適用など、相続対策は異なります。まずは何から整理をして、何をすればよいのかを専門家が一括アドバイス・サポートを行います。
- 遺言書作成を公正証書で作成する場合、別途公証役場の手数料が発生します
- 手続きに必要な書類一式を収集、作成します。
- 生前贈与による不動産名義変更手続き(1物件まで)含みます。登録免許税はお客様の負担になります。
- 遺言証人(2名)の立会には、当事務所の相続スタッフが担当いたします。
- 相続税診断、相続税対策のご提案は、提携税理士が、担当します。
- 上記報酬のほかに、別途実費をいただきます。
- 相続財産が多岐に渡り、詳細な相続税シュミレーションが必要な場合には、別途税理士報酬を頂きます。
- 上記サービス以外の相続対策をご提供した場合には、別途コンサルティング報酬が発生する場合があります。
よくある質問
財産を寄附する(遺贈といいます)先である特定の人や団体を生前に決め「遺言」に書き記すことで、ご自身の意思を実現することができます。当所では、信頼できる遺贈先選定のアドバイスや遺贈先確定のための調査(聞き取り・候補先への同行)によりお客様をサポートすることもできます。
必ずしも遺言書どおりに相続しなくてもよいです。
ただし相続人全員で「遺言書の内容どおりに遺産分割を行わないこと」「新たな遺産分割の方法」について、相続人全員が合意する必要があります。
けして、隠ぺい(隠したり、捨てたりするなど)してはいけません。
遺言書は相続人の権利関係を左右するため、自分にとって不利な遺言書が出てきた場合は焦るかもしれませんが、だからといってそれを隠匿すると、相続欠格者となり、相続権を失うことになります。
遺言書には時効はありません。協議よりも遺言が優先されるので、中身が法的に有効なものであれば、遺言にしたがって遺産を分割し直すことが必要になります。しかし、後から発見された遺言書の内容を確認した相続人全員が、既に行った遺産分割協議の内容を優先させたいと考えている場合は、遺産分割をやり直す必要はありません。
家庭裁判所にて「検認」(家庭裁判所が遺言書を証拠として保全する)の手続きをしなければなりません。後に改ざんを主張され争われることにもなりかねないため、開封せずに速やかに手続きを行うことが必要です。
開封してしまったからといって、開封者の相続権が失われたり、遺言が無効になったりはしません。
ただし開封は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもと行わなければならないとされているため、手続違反の制裁として開封者が、裁判所から5万円以下の過料に処せられる場合があります。
有効になるのは日付が新しいものです。
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」両方がみつかった場合でも、日付が新しいものが有効になります。ただし、自筆遺言証書が正しい書き方になっており、法的に有効と見なされることが条件となります
遺言の当該部分は失効します。
心配がある場合は、「Aが遺言者の死亡以前に死亡した場合はBに相続させる」という予備的な遺言を入れておくとよいです。
いつでも書き直せます。
一度作成したら終わりではなく、自身や家族などの状況の変化に合わせてたえず見直しが必要です。遺言の撤回は、新たに遺言を作成する方法によって行います。自筆証書遺言の場合は遺言を破棄すればよいです。
遺言にもとづき借金を支払うのは長男になります。
最高裁判所の判例によれば、相続人の1人に遺産を全て相続させる遺言により相続分の全部がその相続人に指定された場合、相続債務も全て相続させるという趣旨と解釈すべきであるとしています(最判平成21年3月24日)。(※ただし遺言の趣旨等から、他の相続人にも債務を負担させると解釈される場合は別です。)
相続時のトラブルの元になる下記のようなことは避けたほうがよいです。
1.一部の財産のみの遺言
遺言書に記載のない財産について相続人で分割協議が行う必要が出てきます。
相続人に判断を委ねることで、相続人間で揉めてしまうかもしれません。
「本遺言に記載のない、その他財産の一切を●●●●に相続させる」など遺言書に記載のない財産をどうしてほしいのか具体的に書くことが必要です。
2.不動産を相続人の共有とする遺言
「不動産を長男に3分の2、次男に3分の1ずつ相続させる」などという遺言は、将来、分割の必要性などの有無で揉める可能性があります。
一般的に不動産は共有で相続させるのは避けたほうが得策です。
大丈夫ではありません。
公正証書遺言を作成するには二人以上の証人が必要ですが、これには一定の制限があります。
1.成人でなければ認められません。
2.相続人になると思われる推定相続人や遺言書によって財産を受けることになる受遺者等は認められません。したがって、遺言者の配偶者や子は推定相続人に該当するので証人になることはできません。
自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言で作ったほうがよいです。
他者が手を添えた状態で作成された自筆証書遺言書については、過去に裁判で法的に有効か無効か争われたことがあり、相続のときにトラブルになる可能性があります。
作成できます。
公正証書遺言は、原則として、遺言者から公証人への遺言の趣旨の口授、公証人から遺言者への遺言内容の読み聞かせ(ないし閲覧)が必要とされています。
平成12年の民法改正により、遺言者の口授にかわって通訳ないし自書の要件が、公証人の読み聞かせにかわって通訳の要件が認められたため、口がきけない人や耳が聞こえない人でも遺言能力(遺言の内容を理解し、その遺言の結果どのような効力が生じるがわかる力)があれば、筆談や手話を利用することによって、公正証書遺言ができるようになりました。
自筆証書遺言も作成できます。本人が遺言を行う意思のもと自書をすればよいため、書字能力があれば大丈夫です。
遺言はできます。
・成年被後見人・・・・正常な判断能力が回復しているときにおいて、医師2人以上の立会いがあれば、成年後見人の同意なしに遺言することができます。 その際、医師は被後見人が遺言時に心神喪失の状況になかった旨を遺言書に付記し、署名し、印を押さなければならないことになっています。
・被保佐人、被補助人・・・保佐人や補助人の同意が無くても遺言することができます。
しかし、下記の点に注意が必要です。
「遺言書の作成にあたり、遺言者に遺言能力のあることが重要な前提条件となる」
相続時のトラブル予防のために、遺言時に遺言者に遺言能力があったことが証明できる医師の診断書を取得しておくことが必要です。(遺言時に行う)
※公正証書遺言であったとしても、相続開始後に遺言書の無効について裁判で争われ、遺言書の無効が認められているケースがあります。
※自筆証書遺言の場合は、自ら遺言内容を自書しなければいけないので、一般に内容が合理的で理解可能のものであれば、裁判でも有効とされる傾向にあるが、遺言能力の判断資料として、付言事項を詳しく(財産の分配方法についての理由など)を書いたほうがよいです。
また遺言時に遺言者に遺言能力があったことが証明できる医師の診断書を取得しておくと安心です。
ご訪問・オンラインでの相談もOK!
法律書類の無料相談は
お気軽にお問い合わせください
司法書士と行政書士の専門知識を活かし、
各種許認可申請、相続手続き、登記業務などをサポートしています。
法律書類の作成や手続きに関する無料相談も承っておりますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。

電話で相談する
092-402-6279
平日 9:00-18:00

