相続

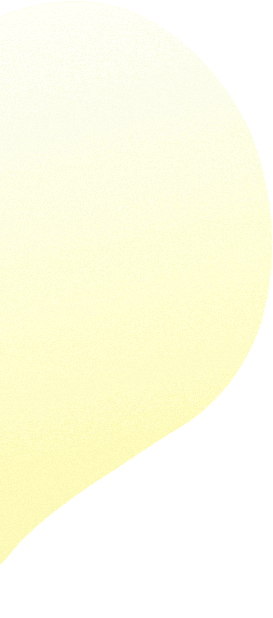
相続が発生し、残されたご家族が
手続きをする期間は
実質3〜4ヶ月
死亡後や相続に伴う手続きはたくさんあり、時間と手間、慣れない言葉に神経を使います。
故⼈を悼むのも束の間、このような⼿続きが⼀気にやってきます。
専⾨家の相談無しにこれらをスムーズに進めることは難しく、
相続⼿続きによる⼿間や想定外の家族間トラブル、
税⾦の⽀払いに疲弊してしまうことは少なくありません。
円満で速やかな相続⼿続きは、故⼈と残された家族が前に進むために⼤切なものです。
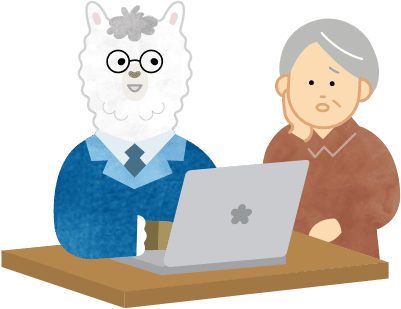
- まだ相続は発生していないが将来的に不安
- 被相続人が不動産(ご自宅を含む)を所有している
- 相続税を払いすぎないように適切に申告したい
- 生前のうちに相続税対策を考えておきたい
- 相続人にできるかぎり多くの財産を残したい
ややこしい、忙しい、⾯倒な
相続⼿続きは
すべて
「はなだオフィス」にお任せください
相続の相談実績
年間100件以上
司法書士と行政書士の連携で
スムーズ対応

電話で相談する
092-433-1160
平日 9:00-18:00
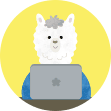
メールで相談する
生前に行う手続き
-
生前贈与
相続対策として財産を事前に贈与
-
遺言書作成
希望通りに財産を分けるための準備
-
成年後見
判断能力が低下した方の財産管理支援
相続時に発生する手続き
-
戸籍収集
相続手続きに必要な戸籍を取得
-
相続放棄
負債を相続しないための手続き
-
各種名義変更
不動産や銀行口座の名義変更
-
相続登記
不動産の名義を相続人に変更
相続は「生前対策」が重要です!生前対策のパッケージプラン
をご用意しております

相続手続きの流れ
- ⼾籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
- 相続財産調査・財産⽬録の作成
- 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
- 全相続⼈から上記案の同意が得られたら、全相続⼈との間で遺産整理委任契約を締結
- 「故●●●遺産整理受任者 花⽥公⼀」名義の預り⾦⼝座を開設
- 各⾦融機関に出向き、残⾼証明書の取得、預貯⾦等の解約、上記預り⾦⼝座への振込予約
- 相続財産精算⼀覧表(相続債務、相続⼈の⽴替⾦、当⽅の報酬等を精算した後の各相続⼈の
取得⾦額が明確化された表)を作成し、各相続⼈に送付 - 相続⼈からの質問に答え、いずれの相続⼈からも異議がないことの確認が取れたら、
各相続⼈が取得する⾦額をそれぞれの⼝座へお振込み - その他、相続不動産等の名義変更⼿続きも同時進⾏で進める
- 相続税の申告(税理⼠担当業務)
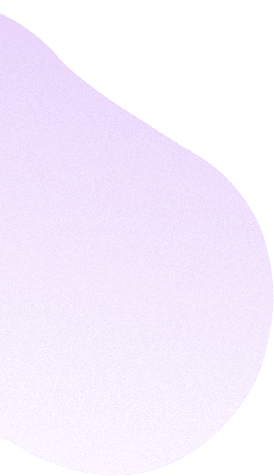

料金について
表記はすべて税別です
| 報酬 | 実費 | |
|---|---|---|
| 相続登記のみ | 60,000円〜 | 登録免許税 |
| 相続放棄申述書 | お一人様につき、50,000円 | 収入印紙800円、 切手400円 |
| 戸籍収集 | 1通 2,000円〜 | 戸籍450円、原戸籍750円 |
| 遺産分割協議書作成 | 1通 50,000円〜 |

ニーズに合わせた
パッケージプランも
ご用意
※相続財産総額・難易度より、報酬額が変動します。
相続手続きサポートバリュープラン
165,000円〜
- 相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続人調査(戸籍収集10通まで)
- 相続財産調査(不動産・預貯金・他)
- 法定相続情報の申請
- 遺産分割協議書作成(相続人5人まで)
- 不動産登記申請一式
- 手続き全般に関する総合サポート
相続手続まるごとサポート
330,000円〜
- 相続手続き
- 不動産の名義変更
- 金融機関手続き
- 遺品整理業務
遺産整理は、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、
手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
- 相続人調査(戸籍収集10通まで)
- 相続財産調査(不動産・預貯金・他)
- 法定相続情報の申請
- 遺産分割協議書作成(相続人5人まで)
- 不動産登記申請一式
- 手続き全般に関する総合サポート
- 金融機関(預金・証券・株式・出資金)等
解約・名義変更手続5件 - 相続財産(不動産売却・運用等)についてのサポート
- 相続税申告(税理士のご紹介)についてのサポート
よくある質問
ふだんなかなか交流がなかったご兄弟が急逝されると、残されたご親族は大変戸惑いますよね。
独身で独り暮らしの方が増えている昨今、そのようなご相談が当所には多数寄せられています。
当所と連携している信頼のおける遺品整理業者や葬儀業者とともにスムーズに相続手続きが進むようにサポートいたします。
【一般的に必要な手続き】
・ご自宅内の整理(預金通帳、有価証券、貴金属、不動産の権利書など貴重品探し、重要書類か否かの見極めなど)・残置物処分
※信頼できる遺品整理業者と連携して行います。
・財産調査(自宅から発見された預金通帳や不動産権利書などプラスの財産、借金やローンなどマイナスの財産を明らかにし相続財産一覧表の作成)
・遺産整理手続(預貯金や不動産の相続手続き)
・賃貸マンションなどの賃貸借契約の解約諸手続き(管理会社との話し合い、原状回復など)
・埋葬手続き
※お墓が遠方にある、ご高齢でお寺まで埋葬にいくのが難しいなど相続人様が行うのが難しい場合は、信頼できる葬儀会社とお客様の間に入り、スムーズに手続きが進むように支援します。
- 紛争性がある→「弁護士」
相続財産をどのように分けるか親族間で話し合いを行ったり、遺言があれば遺言執行者が遺言に沿って相続手続きを行うことになりますが、その際に親族間で意見が対立し、家庭裁判所での調整や裁判に発展する可能性がある場合は最初から「弁護士」に依頼したほうがよいでしょう。
ただし弁護士は他の士業と比較して高い報酬を支払わなければなりませんので、相続人間で揉めるかもしれない心配がある場合はまずは「司法書士」に相談してみましょう。当事務所では紛争にならないために相続人間の意見を調整することができます。
- 相続財産に不動産がある→「司法書士」
相続によって取得した不動産は名義変更(相続登記)をする必要があります。この手続きを行えるのは司法書士と弁護士だけです。登記手続は専門知識と実務経験が必要であり、弁護士に比べて扱う件数の多いのは司法書士です。ぜひ当事務所にご相談ください。
【依頼したほうが良い例】
◆司法書士
・相続財産に不動産があり登記が必要。
・遺産分割協議はこれからだが、揉めるかどうかわからない。
・相続人が多い、音信普通の相続人がいるなど遺産分割協議が大変そう。
・遺産が多岐にわたっており手続きが複雑。
◆弁護士
・遺産相続で既に揉めている。
・遺産分割協議はこれからだが、揉めて調停や裁判になりそう。
◆税理士
・相続税の申告が必要。
・二次相続対策も行いたい。
◆行政書士
・遺産に不動産がなく、遺産が少ない。
・自動車の名義変更が必要。
・とにかく専門家の費用を抑えたい
親族の方だけで解決しようと頑張らないでください。親族の方だけで遺産分割について話し合いをしてしまったことでかえって話がこじれてしまったり、後々までわだかまりが残ってしまうケースが多いです。最初から司法書士などの第三者が間に入ることでスムーズに話がまとまり、紛争を避けることができます。
話し合いを何度も重ねて既に修復不可能となってしまった場合についても念のためご説明します。相続の場合は、いきなり裁判をおこすのではなく、まず家庭裁判所で「調停」という手続きをとります。
調停とは、調停委員という法律の専門家が対立している双方の言い分を聞き、法律的な事例を踏まえた話し合いをすることです。そして話し合いの結果、 調停委員が合意案を出してくれます。この合意案に対立している人全員が納得すれば終了となり、合意案にもとづき遺産分割協議が行えます。納得できない人がいる場合には裁判手続きという流れになります。
ご自分の力だけでは探すのは難しいと思いますので、相続人調査(戸籍や住民票の異動履歴から本人の現在を追う)プロである当事務所にお任せください。
相続人調査をしても行方がみつからない場合は以下どちらかの手続きを行う必要があります。
①家庭裁判所に、行方不明者に代わり遺産分割手続きを行う「不在者財産管理人」を選任してもらう。ただし「不在者財産管理人」は行方不明者の財産を守るために選ばれるため、行方不明者の相続分をゼロとするような手続きは、認められにくい。
②家庭裁判所に、行方不明者が死亡したことにする「失踪宣告」をしてもらう。
行方不明者は死亡した扱いになるため、今度は行方不明者の相続人が遺産分割手続きを代わりに行う。しかし失踪宣告は、生死が7年以上不明であること(災害等は1年以上)という条件がある。
成年後見人と成年被後見人とが同時に相続人となる場合、母親の代理人として遺産分割協議には参加できません。
なぜなら母親と娘の利益が対立する「利益相反」という関係(娘の相続分を多くすれば母親の相続分が少なくなる)になっているからです。
このような場合は、遺産分割協議をするためだけの目的で、別途、特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てなければなりません。そして、選任された特別代理人が母の代わりに遺産分割協議を行うことになります。
進めてはいけません。
遺産分割協議は相続人全員によって行う必要がありますので、認知症の相続人を除外し、その他の相続人だけで遺産分割協議をしても無効となります。
また、認知症の症状が重く判断能力を失っている人が遺産分割協議書に署名押印したとしても、そのような遺産分割協議も当然に無効となります。
認知症の相続人がいる場合は、まずは医師の診断書を取り寄せ、判断能力の状態を必ず確認してください。
認知症の方であっても軽度で判断能力を失っていない場合には、ご本人が遺産分割協議に参加すればよいです。
既に判断能力を失っている場合は、家庭裁判所へ成年後見人等の選任申立をする必要があります。
選任された成年後見人等がご本人に代わり遺産分割協議に参加することになります。
代わりに行うことはできません。
本来ならば未成年者が財産上の法律行為などをする場合には、親権者が法定代理人となって手続きを行います。しかし遺産分割協議の場合は、親権者が未成年者に代わって協議に参加することはできません。なぜなら例えば、父親が亡くなって親権者である母親と未成年の子供どちらともが相続人となる場合、親権者と未成年者の利益が対立する「利益相反」という関係(母親の相続分を多くすれば子供の相続分が少なくなる)になっているので、親権者が未成年者の法定代理人を兼ねることができなくなります。
この場合、未成年者のために特別代理人を家庭裁判所が選任し、未成年に代わって遺産分割に参加することになります。
以下の内容について記載しましょう。
①亡くなった人(被相続人)の氏名
②亡くなった人の最後の本籍
③亡くなった人の最後の住所
④原則としてすべての財産の一覧
※ただし、財産の一部の遺産分割を行うことも可能。
財産の一覧を記載する場合は、個別に詳細まで記載すること。
注)例えば財産が不明確な場合、多額な残金が入った銀行口座に家族が気が付かずに相続税の申告をしてしまうと、過少評価になり、後日相続税の修正申告をする必要があります。財産を調査し確実に漏れがないようにしておきましょう。
◆不動産(土地・建物)
登記事項証明書の内容どおりに正確に記載する
土地であれば所在・地番・地目・地積等
家屋であれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積等
◆金融機関の預貯金
金融機関名・支店名・種類・口座番号・相続開始時の残高
◆有価証券や国債
銘柄、個数、基準価格にもとづく相続開始時の評価額など
◆その他
自動車、加入保険、電話加入権の他、債務も必ず記載する
⑤相続人全員の住所と氏名
⑥相続人全員で話合いをした結果、誰が、どの財産を相続するのか(具体的に記載)
⑦相続人全員の実印を押し、全員の印鑑登録証明書を添付のこと
特に決まっておりません。
用紙の大きさも自由、縦書き・横書きどちらでも可。
ボールペンでの手書き(鉛筆は避けたほうがよい)やパソコンでの作成でも可。
「相続放棄」という方法があります。ただしこの方法をとると、借金などマイナスの財産だけではなく預貯金や不動産などプラスの財産もすべて放棄することになります。
相続の開始があったことを知ってから3か月以内に被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄したいことを申述しなければなりません。
相続税の申告や不動産登記など専門的な手続だけでなく、預金、株、車などの名義変更など一般的な手続を含めると90種類以上もあると言われています。
相続人になります。相続に関して実子と同じ扱いになり、相続分も実子と同じです。
その結果、養子は実の親と養親の両方から相続を受けることができることになります。
相続人となることはできません。妻の連れ子を相続人にしたいのであれば、新しい夫と連れ子との間で養子縁組をする必要があります。
下記ののとおり、どのような場合でも配偶者は必ず相続人となり、民法では配偶者以下の相続の優先順位について下記のように定めています。 ※注意点としては、戸籍上、入籍していることが要件です。したがって内縁関係にある配偶者や離婚した元の配偶者は相続人にはなりません。
相続人
◆第1順位
配偶者と子がいる場合
それぞれ遺産の2分の1ずつを相続する。
配偶者がいない場合は子のみが相続人となる。
子がいれば、父母や兄弟姉妹は相続人になれない。
◆第2順位
子がいない場合
子がいない場合は、配偶者と父母が相続人となり、配偶者が3分の2、父母が3分の1を相続する。
◆第3順位
子も父母もいない場合
子も父母もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となり、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続する。
ご訪問・オンラインでの相談もOK!
法律書類の無料相談は
お気軽にお問い合わせください
司法書士と行政書士の専門知識を活かし、
各種許認可申請、相続手続き、登記業務などをサポートしています。
法律書類の作成や手続きに関する無料相談も承っておりますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。

電話で相談する
092-402-6279
平日 9:00-18:00









