外国人の在留・ビザ関連

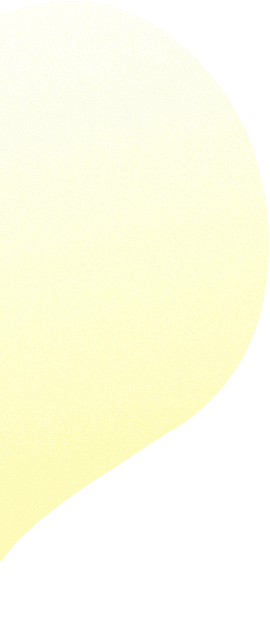
社長の皆さまへ
外国人雇用でこんなことで
お困りではありませんか?

日本進出に伴い、取締役の
在留資格を取得したい
外国人労働者を採用したいが、
就労可能な在留資格が取得できるか不明
転職希望の外国人を採用したいが、
現在の在留資格で就労可能か知りたい
留学生を採用したが、
就労ビザへの変更手続きがわからない
外国人の方の在留資格や就労ビザなどの手続きは
はなだオフィスにお任せください!
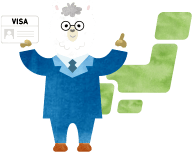
近年、職場で外国人従業員と働くことは珍しくなくなりました。しかし、外国人を正式に雇用するには、適切な在留資格を取得する必要があります。
在留資格の種類は多岐にわたり、申請手続きや必要書類も複雑で、「本当に雇用できるのか?」
「どんな書類を準備すればいいのか?」と悩まれる企業様も多いのではないでしょうか。
そんなときは、ぜひ「はなだオフィス」にお任せください!
在留資格の取得から、外国人雇用に伴う手続きなどトータルでサポートいたします。
スムーズな外国人雇用を実現するために、私たちがしっかりとお手伝いいたします。

サービス一覧
-
在留資格(ビザ)
申請サポート就労ビザ、配偶者ビザ、永住許可などの取得手続き
-
在留資格の
変更・更新手続き現在のビザの変更・更新申請サポート
-
永住・帰化
申請サポート永住権や日本国籍取得に関する手続きサポート
-
就労・経営管理ビザの取得
企業での就労や、日本での起業を希望する方向けのビザ取得支援
-
家族滞在ビザの申請
日本に住む外国人のご家族のビザ取得
-
契約機関の変更手続
(転職手続き)働く場所を変えた場合(転職の場合)の入国管理局に届け出支援
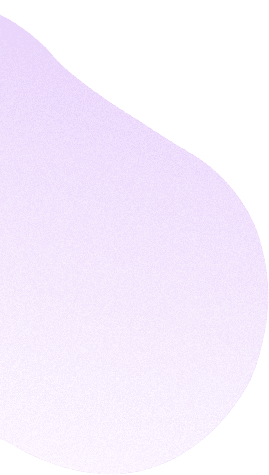
料金について
表記はすべて税別です
| 報酬 | |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請(特定技能1号) | 150,000円~ |
| 在留資格変甲許可申請(経営管理) | 200,000円~ |
| 在留資格更新許可申請(共通) | 80,000円~ |
よくある質問
年齢制限の規定はありませんが、「家族滞在」は日本に在留する家族から扶養を受ける前提の在留資格なので、就業可能な年齢である場合は取得が難しく、子供が18歳以上であれば「留学」の在留資格を取得するように指導を受けることがあります。
「日本人の配偶者等」の在留資格が直ちに消滅することはありませんが、次回更新はできません。すみやかに在留資格の変更申請をすることが相当です。ただし変更を適当と認められる相当の理由がある時に許可が認められます。
婚姻手続をすれば無条件で許可されるものではなく、「日本人の配偶者」という実態が真正なものであるかを審査されます。日本人の配偶者としての活動を行っているとみなされない場合は許可されません。
変更した方がいい場合と、そのままでいいと思われる場合があります。現在のビザでは就労できない内容の職種に転職を希望する場合は配偶者ビザに変更すれば就労制限がなくなるため変更した方がいいですが、結婚後も同じ職場で継続して働く場合などは変更してもしなくても大丈夫といえます。ただし、変更した後に取り消すことはできないので慎重に検討しましょう。
卒業したら在留資格「留学」の活動は完了しているためアルバイトはできません。
卒業したら在留資格「留学」の活動は完了しているため変更手続が必要です。就職活動を続けるためには「特定活動」の在留資格へ変更申請をして、最長1年まで在留することが可能です。
卒業見込証明書の提出があれば前もって申請することができます。ただし在留資格変更許可は卒業証明書の提出後になります。
日本の専門学校を卒業して「専門士」「高度専門士」の称号を付与された場合は基準に適合します。ただし、外国において日本の専門学校にあたる教育機関を卒業した場合は適合しません。
入国しようとする外国人が勤務する本邦の事業所の職員の方が申請できます。また,日本で新たに事業所を設置し,そこで経営を行う若しくは管理に従事する場合には,当該事務所の設置について委託を受けている方(法人である場合にはその職員)が申請することも可能です。
一般的に「在留資格認定証明書交付申請」は1ケ月~3ケ月、「在留資格変更許可申請」及び「在留期間更新許可申請」については2週間~1ケ月を標準処理期間とされています。ただし個々の案件によってかなり差がでることがあります。
雇用主が法人である場合より審査は厳しくなる傾向にありますが、事業に安定性・継続性の根拠があり、契約書を交わした雇用関係について継続性が認められれば許可される可能性があります。
不許可の通知書が届いた場合、通知書の記載のみでは不許可の理由がわからないため出入国在留管理庁に理由を確認します。要件を満たしていないのであれば再申請しても同じ結果になりますが、提出した書類が説明不足だったり誤解をまねくような表現が原因で不許可になっている場合は再申請して結果が変わる可能性がありますので、 不許可理由を解消する書類を準備して再申請することができます。
ご訪問・オンラインでの相談もOK!
法律書類の無料相談は
お気軽にお問い合わせください
司法書士と行政書士の専門知識を活かし、
各種許認可申請、相続手続き、登記業務などをサポートしています。
法律書類の作成や手続きに関する無料相談も承っておりますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。

電話で相談する
092-402-6279
平日 9:00-18:00







